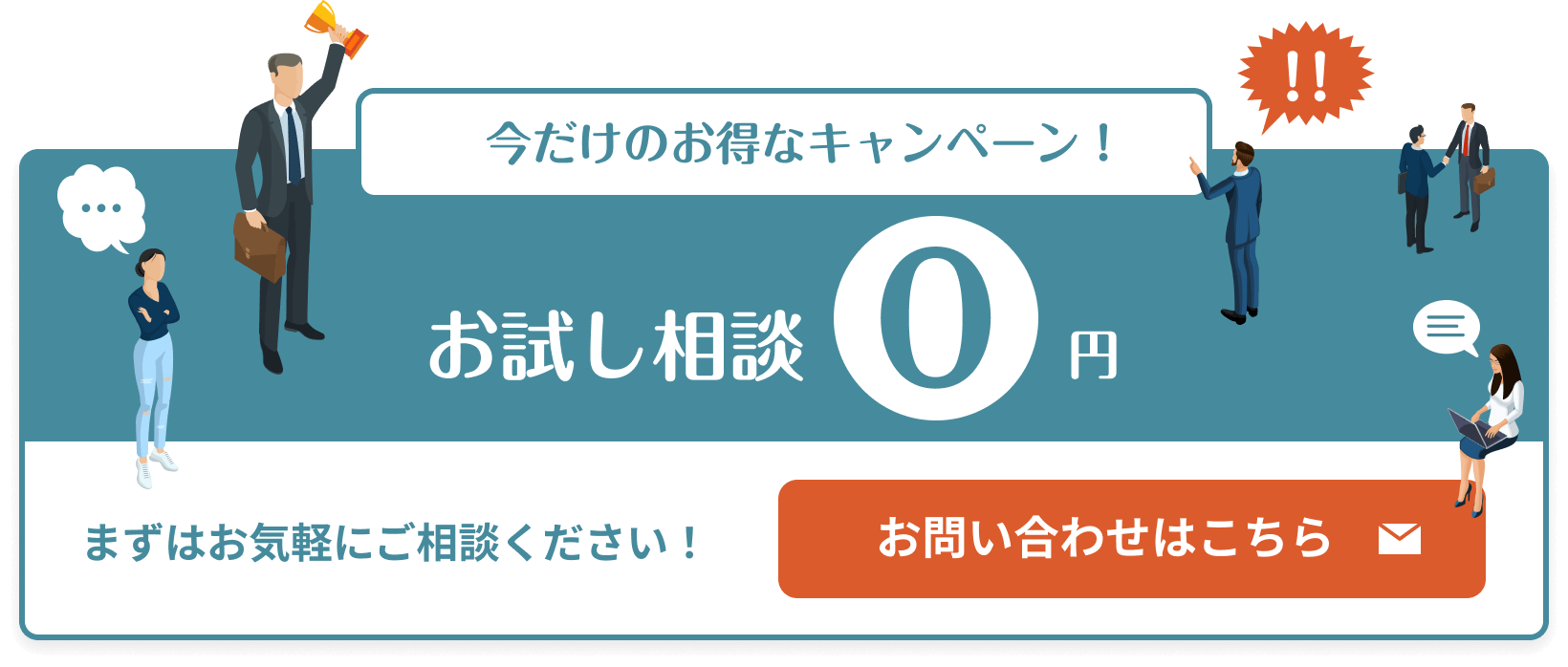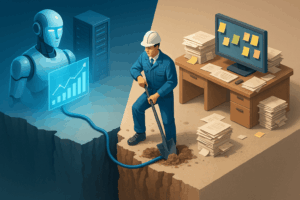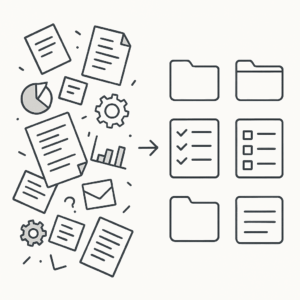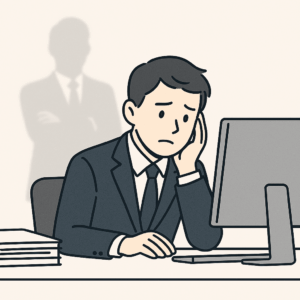Content
コールセンターで「頑張っているのに成果が出ない」と感じていませんか?その原因は、知らずに陥る「手段の目的化」かもしれません。AHT短縮などが目的になってしまう罠の正体と、組織を変える具体的な3つの改善策を現役コンサルタントが解説します。
「オペレーターは毎日、一生懸命に対応しているはずなのに、なぜか顧客満足度が上がらない…」
「高い目標を掲げているのに、現場からは疲弊の声ばかり聞こえてくる…」
コールセンターのコンサルティングでお話を伺うと、多くのマネージャー様がこのようなジレンマを抱えていらっしゃいます。高い志と熱意があるにも関わらず、なぜか成果に結びつかない。その根底には、実は非常にシンプルでありながら、多くの組織が陥りがちな「ある罠」が潜んでいることが少なくありません。
それが、今回のテーマである「仕事の目的と手段を履き違えてしまう」という問題です。これは単なる個人の注意不足ではなく、組織全体のパフォーマンスを静かに蝕む、根深いマインドセットの問題なのです。
「木を見て森を見ず」になっていませんか?コールセンターにおける「手段の目的化」とは
では、コールセンターの現場で起こる「目的と手段の履き違え」とは、具体的にどのような状況を指すのでしょうか。いくつか代表的な例を見ていきましょう。
最も分かりやすい例が、「AHT(平均処理時間)の短縮」です。
AHTの本来の目的は、「顧客満足度を損なうことなく、効率的に多くの入電に対応し、センター運営を最適化する」ことです。決して、ただ時間を短くすること自体がゴールではありません。
しかし、いつしか「AHTを1秒でも短くすること」が至上命題になってしまうとどうでしょう。オペレーターは顧客の話を遮って早口で案内を始めたり、問題の根本解決に必要なヒアリングを省略したりしてしまいます。結果、通話時間は短くなるかもしれませんが、お客様は不満を抱えたまま電話を切り、結局別のオペレーターに再度電話をかけてくる(再入電)。これでは、顧客満足度は下がり、無駄なコストが増えるばかりです。まさに本末転倒と言えるでしょう。
「トークスクリプトの遵守」も同様です。
スクリプトは、応対品質を平準化し、新人でも安心して業務に臨めるようにするための、いわば「地図」や「補助輪」のような存在です。これが本来の目的です。
しかし、これを「一言一句間違えずに読み上げること」が目的だと捉えてしまうと、オペレーターは目の前のお客様の感情や状況を無視した、ロボットのような応対に終始してしまいます。お客様が本当に求めているのは、共感であり、個別の状況に寄り添った解決策です。スクリプトという「手段」に縛られるあまり、「お客様の課題を解決する」という最も大切な「目的」を見失ってしまうのです。
この他にも、「クロスセル」というKPIを追い求めるあまり、不要なオプションを強引に勧めて長期的な信頼を失ったり、「解決率100%」という数字を作るために、お客様が本当に納得していないのに無理やりクローズしたり…といった例は枚挙にいとまがありません。
これらの現象は、オペレーター個人の資質の問題だと片付けられがちですが、実はそうではありません。「分かりやすい数字目標」や「遵守しやすいルール」に頼りすぎてしまう、組織全体の構造や評価制度、そして「何のために我々はこの仕事をしているのか」という根本的なマインドセットの欠如が、この「履き違え」を生み出しているのです。
「目的」を組織のDNAに刻むための3つの処方箋
では、この根深い問題を解決し、組織を正しい方向へ導くためにはどうすれば良いのでしょうか。小手先のテクニックではなく、組織の文化を変えるためのアプローチを3つご提案します。
1.「なぜ?」を共有し、目的を自分事化する文化の醸成
「このKPIは何のため?」「このルールの目的は?」こうした問いを、マネージャー層だけでなく、オペレーター一人ひとりが自分の言葉で語れる状態を目指すべきです。朝礼や研修の場で、ただ数値を共有するだけでなく、「この数字を達成することが、お客様のどんな喜びに繋がり、会社のどんな成長に貢献するのか」というストーリーを繰り返し語り、目的意識を組織のDNAレベルまで浸透させることが不可欠です。
2.評価指標(KPI)の再設計
AHTのような「効率」の指標だけでなく、顧客解決率、VOC(顧客の声)から測る定性的な評価など、「品質」や「顧客への貢献度」を測る指標をバランス良く取り入れましょう。評価の尺度が多角的になることで、オペレーターは「ただ早く切る」のではなく、「いかに顧客を満足させるか」という本来の目的に向かって思考し、行動するようになります。
3.オペレーターへの「権限移譲」
マニュアルでガチガチに固めるのではなく、「お客様にとっての最善は何か」を現場で判断できる裁量権をオペレーターに与えることも極めて重要です。もちろん、そのための十分なトレーニングと、困ったときにすぐに相談できるサポート体制の構築は必須です。オペレーターが自ら考え、行動する機会を得ることで、「言われたことをこなす作業者」から「顧客の問題を解決する当事者」へと、マインドセットそのものが劇的に変化していくはずです。 先ずは高スキルのオペレーターから始めてみましょう。
今回お話しした「目的と手段の履き違え」は、どのコールセンターでも起こりうる普遍的な課題です。もし、あなたのセンターで少しでも心当たりがあるならば、それは個人の問題ではなく、組織の仕組みを見直す絶好の機会なのかもしれません。
外部の客観的な視点を入れることで、当たり前だと思っていた業務の中に潜む「目的と手段のズレ」が明確になることは少なくありません。一度、私達と一緒に、皆様のセンターが本当に目指すべきゴールは何か、そしてそのための最適な道のりは何かを整理してみませんか。必ずや、明日からのセンター運営を大きく変えるヒントが見つかるはずです。
この記事を書いた人
コンサルタント永久 圭一keiichi Nagaku
債権管理業務に計15年、コールセンター事業者2社(計13年)に在籍
SVや地方センターや在宅業務センターのセンター長等に従事後独立
保有資格
 DX推進パスポート
DX推進パスポート JDLA Deep Learning for GENERAL (G検定)
JDLA Deep Learning for GENERAL (G検定)COPCリーンシックスシグマイエローベルト
- コンプライアンス・オフィサー・消費者金融コース
- ビジネスキャリア検定(労務管理)