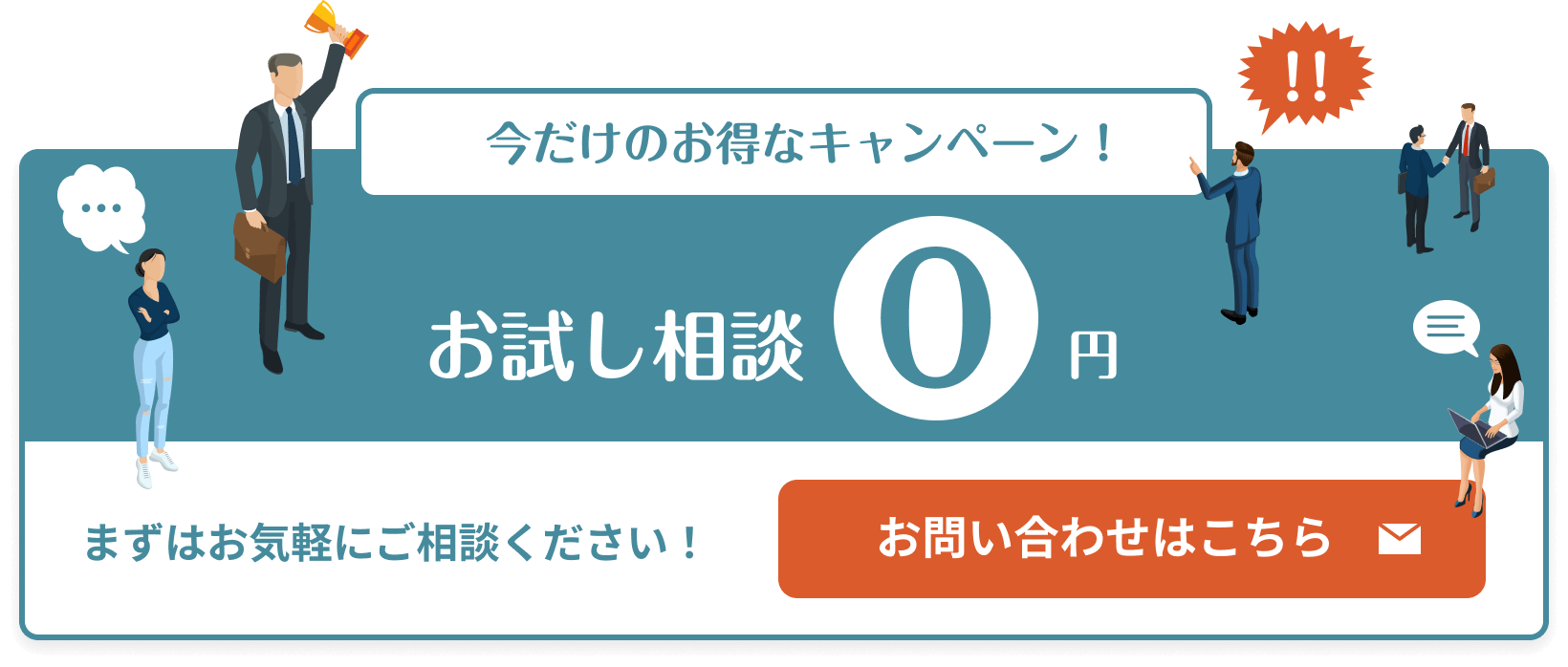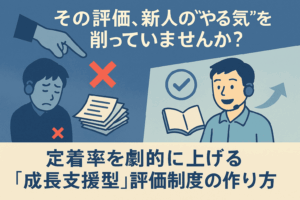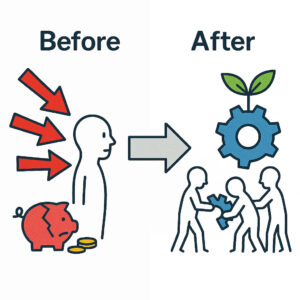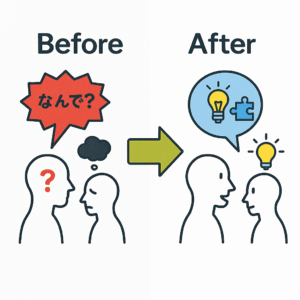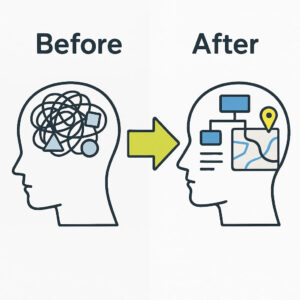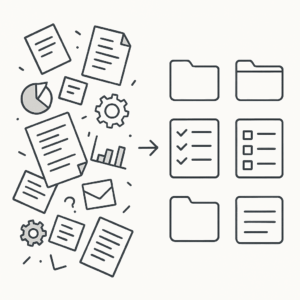Content
新人のミスが起きた時、つい「誰のせい?」と考えていませんか?その「Bad探し」が、実は新人の挑戦意欲を奪い、早期離職に繋がる危険な文化です。ミスを個人の責任で終わらせず、チームの学びに変える「Problem思考」を専門家が解説。
研修を終えたばかりの新人オペレーターが、お客様からクレームを受けた。この時、あなたのセンターではどのような会話が交わされるでしょうか。
「原因は何だ。誰がやった?」と“犯人”を探し、個人の責任を追及するのか。それとも、「なぜこの問題が起きたのか。何を学べるか?」と“課題”として捉え、未来の糧とするのか。
この小さな分かれ道こそが、新人が「たった数ヶ月で退職届を出す」のか、「未来のエースへと成長する」のかを分ける、決定的な分岐点なのです。今回は、多くの組織が陥りがちな「Bad(悪)」探しという病と、それを乗り越え、新人が安心して成長できる「Problem(課題)」思考という処方箋についてお話しします。
その問題、あなたは「裁いて」いませんか?
考えてみてください。新人オペレーターのミスが発覚した時、私たちはどのような行動を取りがちでしょうか。本人を呼び出し、「なぜこんなことをしたんだ」「何度言ったら分かるんだ」と、その行動を「悪いこと(Bad)」として断罪し、原因を「能力の低い個人」に求めてはいないでしょうか。
この「Bad探し」の文化が蔓延した組織は、必ず深刻な病にかかっていきます。
病状1:失敗の隠蔽
「ミスをしたら、怒られる、評価が下がる」という恐怖が支配すれば、オペレーターはミスを報告しなくなります。特に、まだ心理的な繋がりが薄い新人は、「怒られるくらいなら黙っていよう」と、致命的な問題を一人で抱え込みがちです。
病状2:挑戦の文化の消滅
新しいトークを試して失敗すれば、「余計なことをした」と「Bad」の烙印を押される。そんな環境では、新人はマニュアルに書かれた以上の挑戦をしなくなります。言われたことだけをこなすようになり、組織から活力が失われていきます。
病状3:新人の早期離出
常に「裁かれる」というプレッシャーの中で、安心して働くことはできません。このような減点主義の文化で、最初に組織を見限るのは、他ならぬ新人たちです。改善意欲の高い優秀な人材ほど、早々に退職を決意してしまいます。
「Problem」として捉え、未来の糧にする
では、どうすればいいのか。答えは、問題を「Bad」ではなく「Problem(課題)」として捉え直すことです。「Problem」とは、本来あるべき姿と現状との間に存在する「ギャップ」を指す、客観的な言葉です。
同じ誤案内という事象も、「Problem」として捉える組織では、問いの立て方が、「誰が悪いのか?」から「なぜ、このギャップ(Problem)は発生したのか?」に変わります。
この問いを立てた瞬間、犯人探しは終わり、真の「原因究明」が始まります。
「マニュアルの、あの部分の記述が分かりにくかったのではないか?」
「そもそも、研修でこのケースについて十分に触れていなかったのでは?」
このように、問題を個人の資質から切り離し、「仕組み」の課題として捉えることで、新人は安心して事実を話せるようになり、SVやマネージャーは、その事実に基づいて具体的な改善策を考えることができるのです。
「Bad」を探せば、見つかるのは「犯人」だけです。しかし、「Problem」を分析すれば、そこには組織と新人を共に成長させる「学び」という、未来への資産が見つかるのです。
「評価」から「改善」へ。組織のOSを入れ替える3つのアクション
この「Problem」思考を組織に根付かせ、新人が安心して挑戦できる文化を育むための具体的なアクションを3つご紹介します。
1.インシデントレポートのフォーマットを変える
「発生者」「反省点」といった個人を主語にする報告書をやめ、「①発生した事象」「②理想の状態」「③ギャップを生んだ構造的要因」「④再発防止策」といった未来志向のフォーマットを導入します。報告の目的が「謝罪」から「改善提案」へと変わります。
2.「非難なき事後検証」の文化を導入する
問題発生時に関係者が集まり「誰がやったか」は一切問わず、「なぜそれが可能になったか」というシステムの脆弱性だけを分析する会議体を設けましょう。この場では、失敗を正直に話した新人がヒーローです。
3.リーダーの質問を「Why」から「What/How」へ変える
SVが、反射的に「なぜミスしたの?(Why)」と詰問するのをやめ、「ミスが起きた時、何が見えていた?(What)」「その時、どう判断した?(How)」と、事実に焦点を当てた質問をするよう、トレーニングを行います。
「採用と研修の繰り返し」に悩むSV・マネージャーのための解決策
問題が起きた時に、それを個人の「Bad」として断罪するのではなく、組織の「Problem」として学びの機会に変えられるか。その文化こそが、新人が安心して根付き、成長できる土壌なのです。
私たちWanderinConsultingは、この根深い課題を解決するため、コールセンターの現場から生まれた専門的なプログラムをご提供します。
新人オペレーターが辞めない組織を作る「定着率改善」実践プログラム
こんなお悩みはありませんか?
- 手塩にかけて育てた新人が、研修期間中や独り立ち直後に辞めてしまう。
- 採用コストと研修コストがかさみ、センターの収益を圧迫している。
- SVが新人への指導や面談に時間を取られ、本来のマネジメント業務に集中できない。
- 場当たり的な指導が多く、誰が教えるかによって新人の成長に差が出てしまう。
本プログラムが提供する3つの価値
1.財務的負債の解決
高い離職率という「財務的負債」を直接的に解決し、具体的な採用・研修コストの削減を実現します。
2.マネージャーの負担軽減
SVやマネージャーの精神的・時間的負担を大幅に軽減し、本来注力すべき品質向上や戦略立案のための時間を創出します。
3.「仕組み」の構築
一過性の研修ではなく、貴社に「人が定着する仕組み」そのものを構築し、持続可能で安定したセンター運営を可能にします。
サービス内容(3ヶ月間のステップ)
私たちのプログラムは、以下の3つのフェーズで、貴社に「人が定着する仕組み」を構築します。
Phase 1: 診断フェーズ(現状把握・課題特定)
スタッフへの匿名アンケートやマネージャーへのヒアリング、各種KPI、マニュアル、実際の通話音声データなどを分析。 貴社の離職に関する本当の課題を特定し、「組織診断レポート」としてご提出します。
Phase 2: 計画フェーズ(改善計画の策定)
診断レポートに基づき、貴社と共同で、現場で実行可能な具体的な改善アクションプランを策定します。
Phase 3: 実行支援フェーズ(仕組みの導入と定着)
アクションプランを現場で実行するために必要なマネジメントスキルを、実践的なトレーニング形式(例:2時間×3回)で提供します。
プログラム概要
- 対象: Eコマース(通販)業界のコールセンター(15〜75席規模)に従事するマネージャー、SV様
- 期間: 約3ヶ月
- 価格: 150万円(税抜)
まずは、貴社の課題を私たちにお聞かせください。
私たちのコンサルティングは、単なる「コスト」ではありません。企業の財務的損失を食い止め、未来の成長に繋がるリターンが明確な「投資」です。 初回のご相談では、貴社の状況に合わせたROI(投資収益率)シミュレーションもご提示可能です。 まずはお気軽にお問い合わせください。
この記事を書いた人
コンサルタント永久 圭一keiichi Nagaku
債権管理業務に計15年、コールセンター事業者2社(計13年)に在籍
SVや地方センターや在宅業務センターのセンター長等に従事後独立
保有資格
 DX推進パスポート
DX推進パスポート JDLA Deep Learning for GENERAL (G検定)
JDLA Deep Learning for GENERAL (G検定)COPCリーンシックスシグマイエローベルト
- コンプライアンス・オフィサー・消費者金融コース
- ビジネスキャリア検定(労務管理)